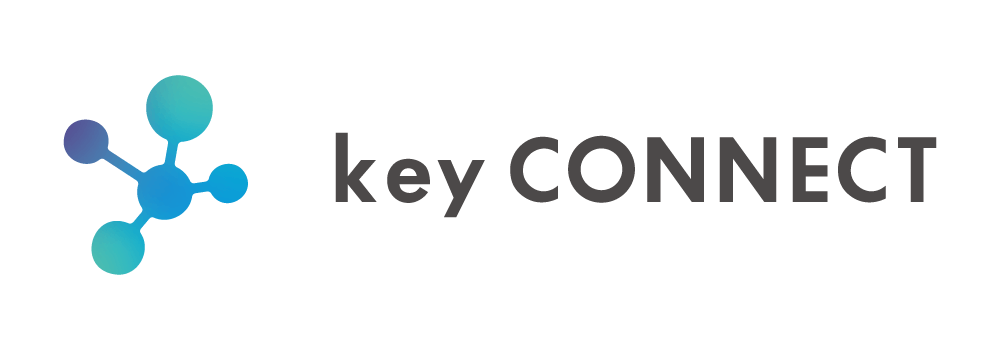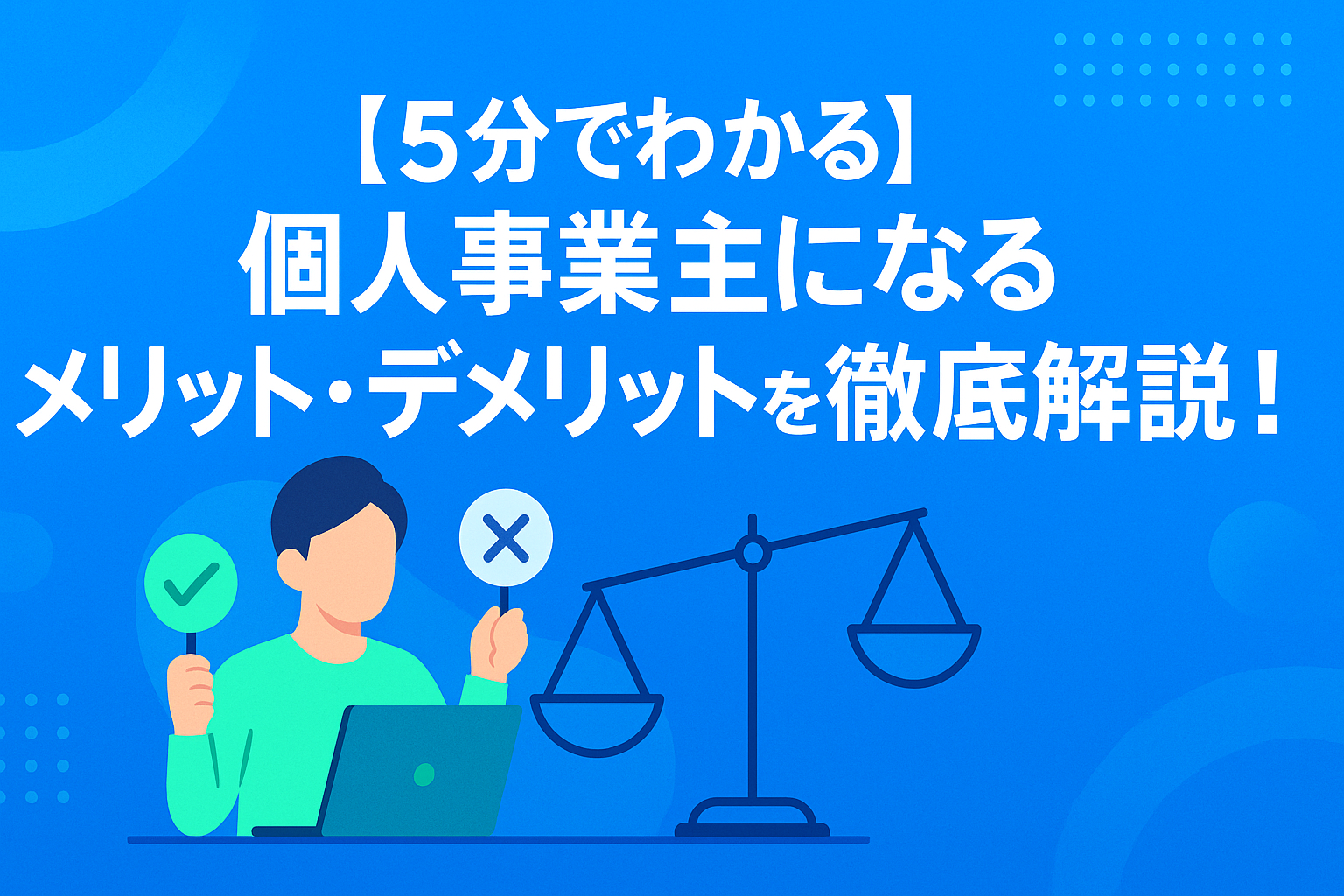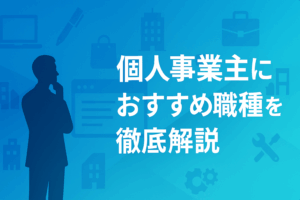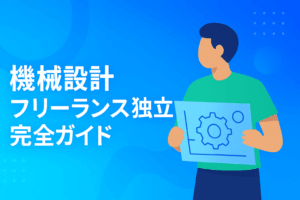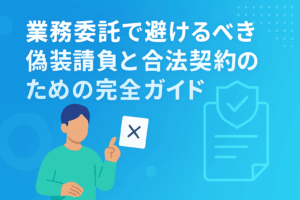「個人事業主になりたいけれど不安がある」「会社員との違いやデメリットが知りたい」とお悩みではありませんか?
この記事では、個人事業主の基本から、メリット・デメリット、リスクへの対策まで徹底解説。読めば、自分に合う働き方かどうか明確な判断ができるようになります。
個人事業主とは何か 基本を確認しよう

個人事業主とは、会社などの法人を設立せずに、自分の名前で事業を営む人のことを指します。日本においては、フリーランス、自由業、自営業などと呼ばれるケースも多く、ITエンジニア、デザイナー、ライター、小売業、飲食業など、さまざまな業種で活躍する人がいます。
個人で税務署に開業届を提出するだけで始められる手軽さが特徴で、規模も大きく制限がありません。ただし、事業にかかる責任やリスクも全て自身が負うため、事前の理解が重要です。
個人事業主と会社員の違い
個人事業主と会社員(従業員)の違いを下表に整理しました。
| 区分 | 個人事業主 | 会社員 |
|---|---|---|
| 収入 | 売上や収益は自分次第、変動しやすい | 毎月決まった給与が支給される |
| 税金 | 自分で確定申告が必要 | 会社が源泉徴収・年末調整を対応 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金 |
| 雇用関係 | 自分が事業主 | 会社と雇用契約 |
| 働き方 | 時間・場所など働き方を自由に選択可能 | 勤務時間・場所が固定される |
| 保障 | 労災や失業手当なし | 労働保険や失業手当あり |
このように、個人事業主は自分の裁量で働ける半面、収入や社会的な保障といった面で自己責任が大きくなるという違いがあります。
個人事業主の開業手続きや流れ
個人事業主として事業を始める場合、基本的には下記のようなステップで手続きを行います。
- 税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出
- 青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」を提出
- 必要に応じ、事業内容に合った許認可・届出を各行政機関へ提出
- 屋号(ビジネスネーム)が必要な場合は、開業届に記載
- 業種によっては保健所や都道府県への手続きも必要
開業届は自宅近くの税務署で無料でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。提出から事業の開始までは最短即日で可能です。
なお、開業後は定期的に帳簿の記帳や確定申告を自分で行う必要があるため、早めに会計ソフトなどの導入を検討することが推奨されます。
個人事業主のメリットをわかりやすく紹介

自由度の高さと働き方の選択肢
個人事業主は、業務内容や働く時間、場所を自分自身で自由にコントロールできるという大きなメリットがあります。例えば、朝型・夜型など自分のライフスタイルに合わせて仕事を進めたり、カフェや自宅、レンタルオフィスなど好きな環境を選ぶことも可能です。また、複数の仕事やプロジェクトに同時に関わるなど、多様な働き方も選択できます。ライフステージの変化や家庭の事情にも柔軟に対応できるため、自分らしいキャリアやワークライフバランスを重視したい方には最適です。
所得控除による節税効果
個人事業主は、経費計上や青色申告特別控除などの制度を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できる点も大きな魅力です。事業に関わる費用(交通費・通信費・接待交際費など)は経費として計上でき、課税対象となる所得を減らすことが可能です。下記の表は主な節税手法とその概要です。
| 節税方法 | 内容 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 必要経費の計上 | 事業の運営に直接要した費用を所得から差し引く | 税負担の軽減・実質的な可処分所得の増加 |
| 青色申告特別控除 | 正規の簿記で記帳・青色申告承認を受けた場合65万円控除 | 更なる所得控除で節税効果が高い |
| 小規模企業共済やiDeCoの活用 | 将来の備えとして積み立てた金額を全額所得控除 | 老後資金の準備と同時に年間の税金も節約 |
このように経費や様々な控除を活用することで、会社員では得にくい柔軟な節税が実現します。
少ない初期費用と事務手続き
個人事業主は会社設立に比べて初期費用がほとんどかからず、手続きも非常に簡単です。登記費用や定款作成、法人口座開設といった手間もなく、必要書類を税務署等に提出するだけではじめられます。また、維持費も安価で済み、毎年の決算公告など義務的な手続きも必要ありません。最初に思い立ったときから比較的短期間でスタートできるため、「まずはスモールスタートで挑戦したい」という方にもおすすめです。
人脈やスキルアップの機会
個人事業主として活動することで、取引先や異業種交流、コミュニティ参加を通じて新しい人脈を積極的に広げやすいのも特徴です。個別受注やプロジェクト単位の仕事が多く、様々な業種や職種の人と出会えるため、自然とコミュニケーション能力や専門スキルが向上しやすい環境といえます。加えて、自分の努力や実績がダイレクトに評価されるため、モチベーション高く自己成長に挑戦できる点もメリットです。
個人事業主のデメリットを徹底解説

社会保険や年金の不利益
個人事業主は社会保険や年金制度において、会社員と比較して不利益を被りやすいのが大きなデメリットです。 会社員であれば厚生年金や協会けんぽ・健康保険組合の保険に加入するのが一般的ですが、個人事業主の場合は国民年金と国民健康保険となります。これにより、将来の年金受給額や保険の手厚さに差が生じます。
厚生年金ではなく国民年金となる理由
個人事業主は厚生年金に加入できず、国民年金のみの加入となります。 厚生年金は労使折半で保険料を負担しますが、国民年金は全額自己負担です。また、国民年金は受給額が厚生年金よりも低いため、将来的な年金収入が少なくなる傾向があります。
| 区分 | 対象者 | 保険料支払方法 | 将来の年金額(目安) |
|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 会社員・公務員 | 労使折半 | 月額約14万円(平均年金受給額) |
| 国民年金 | 個人事業主・自営業 | 全額自己負担 | 月額約6.5万円(満額支給時) |
健康保険は国民健康保険になる
個人事業主は会社員とは異なり、原則として国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険は保険料が前年所得により大きく変動するうえ、扶養制度がなく家族一人ひとりに保険料がかかります。協会けんぽや健康保険組合と比べて手厚い保障が受けにくいケースもあり、出産手当金などの制度もありません。
収入の不安定さとリスク
個人事業主の大きな課題は、月々や年単位での収入が安定しづらいことです。 クライアントや案件の都合、景気の変動など外部要因を受けやすく、自身の営業力やスキル次第で収入が大きく変動します。また、病気やケガなどで働けなくなった場合にも、会社員のような傷病手当金や有給休暇による保障が少ないため、生活への影響がダイレクトに及びます。
| リスク事例 | 会社員の場合 | 個人事業主の場合 |
|---|---|---|
| 病気・ケガによる休業 | 傷病手当金・有給休暇が活用可能 | 休業中は収入ゼロ、保障制度は最小限 |
| 景気悪化・案件減少 | 給与は比較的安定 | 売上減による収入の急減あり |
信用力の低さと融資の難しさ
個人事業主は会社員や法人と比べて社会的信用力が低い傾向にあります。 そのため、住宅ローンや事業資金を金融機関から調達しようとした場合、審査が厳しくなることが多いです。また、クレジットカードの申込や賃貸契約時も「安定した収入」が求められる場面では不利になりやすいです。開業間もない時期や、収入証明が安定しない時期などは特に注意が必要です。
確定申告や帳簿管理の負担
個人事業主は、毎年「確定申告」を自ら行う必要があり、帳簿の記帳・管理業務も全て自身で行わなくてはなりません。 特に青色申告を選んだ場合、複式簿記による記帳や各種帳簿の保存義務、経費計上の判断など、正しい知識と手間が求められます。ミスがあると追徴課税やペナルティのリスクもあります。また、これらに時間を取られることで本業に割ける時間が減ってしまうケースも多いです。
| 業務内容 | 所要時間・手間 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 帳簿記帳 | 日々の仕訳・レシート等の保存 | 記帳不備による税務署からの指摘 |
| 確定申告 | 毎年1~3月に申告作業 | 申告漏れや納税ミス・遅延による加算税 |
労働時間や休日の確保が難しい
個人事業主は自分の裁量で働ける一方、繁忙期や案件対応で長時間労働や休日返上になりやすいという課題も抱えています。 特に受注量が増えた際やクライアント対応が重なる時期は、労働時間が大幅に伸びてしまうことも。法定労働時間や有給休暇の制度などがないため、自己管理が難しい場合は過労や体調不良を引き起こすケースもあります。「仕事とプライベートの線引き」が苦手な方には大きなストレスになる可能性があります。
個人事業主に向いている人の特徴

個人事業主として活躍しやすい人物には共通する特徴があります。ここでは、どのような人が個人事業主に向いているのかを具体的に解説します。また、必要とされるスキルや資質なども詳しくご紹介します。
自己管理能力の高さ
個人事業主として成功するためには「自己管理能力」が非常に重要です。会社員とは異なり、就業時間や業務量、目標管理などを自分で決めて推進しなければなりません。納期やスケジュールの管理、取引先との連絡調整なども業務の一部となるため、計画的に物事を進めることができる人が向いています。自宅やコワーキングスペースなど、働く場所を自由に選べる反面、自己を律する意識が求められます。
| 必要な管理能力 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 時間管理 | 効率的なスケジュール作成、納期遵守 |
| 業務管理 | 複数案件のタスク把握、優先順位付け |
| モチベーション維持 | 目標設定と自己評価による成長意欲の継続 |
挑戦心や柔軟な発想
変化の激しい市場や業界に適応するためには、「挑戦心」と「柔軟な発想」が不可欠です。個人事業主は新たな事業展開や顧客獲得に自らチャレンジし、アイデアを形にして実行していく力が求められます。失敗を恐れず前向きに改善し続ける姿勢こそが、安定した売上の確保や新規取引先の獲得につながります。また、自分の得意分野にこだわるだけでなく、社会の需要やトレンドにも敏感であることが重要です。
| 求められる資質 | メリット |
|---|---|
| 失敗を恐れない挑戦心 | 新しい取引やジャンルに積極的に参入できる |
| 発想の柔軟性 | 顧客ニーズの変化や時代の流れにスムーズに対応 |
| 成長欲求 | スキルアップや人脈形成につながる |
このように、高い自己管理能力と前向きな挑戦心、そして変化に適応できる柔軟な思考を持つ人ほど、個人事業主として長く安定した事業運営が可能となります。自分の強みを活かし、主体的に動ける人材が求められています。
会社設立(法人化)との違いと注意点

有限会社・株式会社との比較
個人事業主と法人(株式会社・合同会社など)には、法律上の扱いや税制、社会的信用など多くの違いがあります。以下の表は、主な違いを整理したものです。
| 区分 | 個人事業主 | 株式会社/合同会社(法人) |
|---|---|---|
| 設立コスト | 無料(開業届のみ) | 登録免許税・定款認証料など約20万円~ |
| 設立手続き | 税務署などへ届け出 | 法務局や公証役場など様々な手続きが必要 |
| 税金 | 所得税(累進課税) | 法人税(一定率) |
| 社会的信用 | 低い | 高い |
| 社会保険 | 任意 | 原則加入義務あり |
| 赤字の場合の責任 | 無限責任 | 有限責任 |
| 決算公告義務 | なし | 株式会社はあり |
| 役員報酬 | なし | 設定可能(節税対策に有効) |
このように、法人は設立時・運営時のコストが高く手続きも煩雑ですが、社会的信用が高く、赤字でも責任が有限です。また、所得が増えるほど法人化による節税メリットが大きくなります。一方、個人事業主は開業が簡単で維持費も低いため、スタートアップや小規模事業に向いています。
個人事業主から法人化する際のタイミング
個人事業主から法人化を検討するタイミングは、主に「売上・利益の増加」と「社会的信用の必要性」がポイントです。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 課税所得が年間600万円~800万円を超え、累進課税で税負担が増えてきたとき
- 大手企業との取引のため社会的信用が必要なとき
- 従業員を増やして組織的な経営を目指すとき
- 節税対策として役員報酬や経費計上の幅を広げたいとき
- 家族を役員にして所得分散を行いたいとき
しかし、法人化すると事務作業や社会保険料の負担、赤字でも法人住民税が発生するなどのデメリットもあるため、充分なシミュレーションや専門家への相談が重要です。
個人事業主のデメリットをカバーするための対策

会計ソフトや税理士の活用
確定申告や帳簿管理の負担を軽減するためには、会計ソフトの導入が非常に効果的です。freeeや弥生会計などのクラウド会計ソフトを活用すれば、領収書のデータ取り込みや自動仕訳、申告書類の作成がスムーズに行えます。
また、税務の専門知識が不足している場合や複雑な経理処理が発生する場合は、税理士に相談・依頼することも有効です。税理士を活用することで、節税のアドバイスや正確な申告が可能となり、余計なトラブルやペナルティを防ぐことができます。
| 対策方法 | メリット |
|---|---|
| 会計ソフトの利用 | 経理・確定申告が効率化される |
| 税理士への依頼 | 正確な節税・申告が可能になる |
ビジネス保険や融資制度の利用
収入の不安定さやリスクへの備えとして、ビジネス保険や公的な融資制度を活用することが大切です。
日本政策金融公庫や商工会議所などが実施する創業融資や事業資金サポートをうまく活用しましょう。資金繰りに余裕が生まれることで、仕事が不安定なときにも安心して事業を継続できます。
また、賠償責任保険・所得補償保険など、予期せぬ事故や病気で働けなくなった場合に備えた保険へ加入しておくと安心です。事業活動に応じた保険の活用で、リスクを最小限に抑えることができます。
| 活用できる制度・保険 | 主な目的 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫の融資 | 開業資金や運転資金の調達 |
| 所得補償保険 | 病気・ケガによる収入減対策 |
| 賠償責任保険 | 対人・対物事故の補償 |
社会保険の任意加入やiDeCo活用
個人事業主は原則として国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、老後や万一の備えが薄くなるデメリットがあります。
そのため、自主的に社会保険を補完する対策が不可欠です。例えば、国民年金基金やなどに加入することで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能です。
また、一定条件を満たせば小規模企業共済なども利用できます。これにより、引退時の資金として積み立てることができ、退職金の代わりにもなります。
| 制度 | 特徴 |
|---|---|
| iDeCo | 将来の年金上乗せと所得控除による節税 |
| 国民年金基金 | 基礎年金を補う任意加入の年金制度 |
| 小規模企業共済 | 退職金に相当する共済金を積み立てられる |
これらの制度をうまく活用することで、個人事業主が抱える社会保障や資金面でのデメリットを効果的にカバーし、安心して事業運営を行うことができます。
まとめ
個人事業主は自由度が高く所得控除などのメリットがある一方で、社会保険や年金の不利益、収入の不安定さ、信用力の低さなどデメリットもあります。対策を講じながら自身の特性や将来設計に合わせて、会社員や法人化との違いも理解し、最適な働き方を選びましょう。